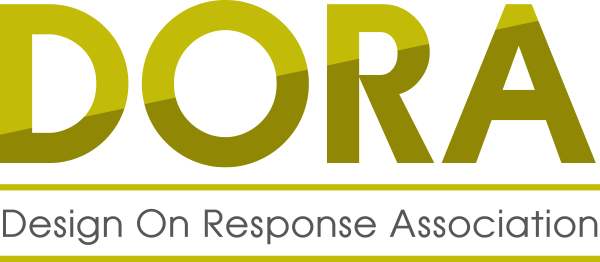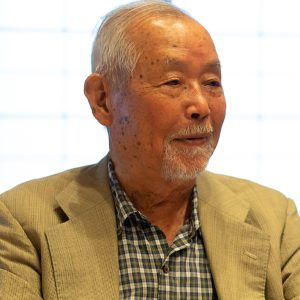イタリア北部の街・ピエトラサンタを拠点に創作活動を展開されている彫刻家の安田侃(かん)氏。
その作品は世界中の都市の公共空間や、美術館、建物に設置されており、特に「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄(びばい)」は、故郷である北海道・美唄の名所として多くの人々が訪れています。
2025年秋、イサム・ノグチ賞を受賞した現代彫刻の巨匠に、作品に込める想いなど、幅広いお話を伺いました。
故郷の街・美唄

彫刻家の安田侃氏
Q. 安田先生は北海道の美唄のご出身なのですね。
安田侃氏(以下、安田)はい。美唄は北海道の空知地方に位置する街で、かつては炭鉱の街としてとても賑わい、1950年代半ばの最盛期には三井や三菱など7つの炭鉱と、9万人以上の人口を擁していました。しかし、1950年代後半から国内石炭産業が不況になると、美唄の炭鉱も次々に閉鎖されていき、1973年(昭和48年)に最後の炭鉱が閉山したという歴史があります。
炭鉱で栄え、その後衰退していった街の記憶。そしてここで暮らしていた大勢の人々の想い。それらを未来へと受け継ぎながら、人・自然・芸術の新しい関係をつくろうというコンセプトで、この街に1992年(平成4年)にオープンしたのが「安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄」です。ここは廃校となった旧美唄市立栄小学校を含む7万㎡という広い敷地の中に私の彫刻が40点以上あり、開館以来多くの人々に親しんでいただいています。この施設では「こころを彫る授業」という、参加者が自分自身と向き合いながら大理石や軟石を彫るイベントを開催しているのですが、私自身もこのイベントで皆さんと交流することをとても楽しんでいます。
Q. 安田先生から直接教えていただけるのですね。それは素敵です!(編註:安田侃氏が講師を務める特別会については美術館の公式HPを参照)
Q. 美唄には「アルテピアッツァ美唄」の近くにも安田先生の作品がありますね。
安田 はい。街の中心地から少し山に入った、かつて三菱美唄炭鉱があった跡地(現:我路ファミリー公園)に、私が「モニュメント」として最初に手掛けた「炭山(やま)の碑」(1980年)があります。「炭山(やま)」というのは、石炭採掘に従事する人々の仕事場と住居を中心として形成された共同体のことです。三菱美唄炭鉱で働いていた人々とその家族たちは、1972年(昭和47年)の閉山後、ここを離れて全国に散っていったのですが、その後も毎年お盆になるとお墓参りのためにこの場所に帰ってきていました。しかし、多くの人々が働き、暮らした炭山の痕跡は数年後にはすべてなくなり、そこにはただ自然の景色が広がるだけ、という状態になっていました。そこで「私たちが暮らした炭山の記憶を残すものをつくりたい」という人々の声が高まり、閉山から6年後の1978年(昭和53年)、当時イタリアで創作活動をしていた私のところにモニュメントの制作依頼がきたのです。
制作にあたり、私はどのようなモニュメントがこの場所に相応しいのか、とても悩みました。そしてつくり上げたのが、空に伸びる3本の立像です。かつて美唄の炭鉱には、日本人だけでなく中国や朝鮮半島出身の人々も多く働いており、炭鉱事故によりたくさんの命が失われました。今も地底に埋もれたままとなっている彼ら炭鉱事故犠牲者たちの魂を吸い上げて、天に放してあげようというのがコンセプトです。このコンセプトは最初に考えたのですが、それをひとつの形にするために何カ月間も試行錯誤を繰り返しました。完成した3本の立柱の直径はそれぞれ80cmあるのですが、これ以上では重圧感がありすぎ、それ以下では頼りなさすぎて駄目なんです。この「80cmの立柱」というのは、考え抜いて、大樹や大理石など、いろいろなものに抱きついて探し求めた結果、たどり着いた形なのです。

「炭山の碑」(北海道、美唄/1980年)**
彫刻家への道
Q. 安田先生は1945年(昭和20年)生まれということで、戦後の復興を支えた炭鉱の街・美唄が活気にあふれていた時代に幼少期を過ごされています。彫刻家になろうと志したのもその頃でしょうか?
安田 いえ、子供の頃は野球選手になるのが夢で、野球ばかりやっていました。なかなか良い選手だったんですよ(笑)。高校3年生の頃は「実業団に入って野球がしたい」と思っていました。実際にある企業からスカウトもあったのですが、父親の「ノンプロでは通用しないだろう」という考えもあって実現せず、卒業後は北海道教育大学岩見沢分校に進みました。
教育大学は学校の先生を養成するためにあらゆる教科があるのですが、私は「体育の先生になって野球部の監督になろう」と思い、入学後の教科選択の際に体育コースに並んだのですが、私のひとり前で定員になって締め切られてしまいました。それで「どうしようか?」と考えたのですが、子供の頃から野球以外に「絵が上手だね」とよく褒められてきたことを思い出しました。そこで「美術コースに行こう」と思って教室を訪ねたところ、上半身裸で巨大なカツラの木と向き合い、黙々と格闘している人がいたのです。私がその姿に圧倒されていると「君はここに入りたいのか?」と声を掛けられました。この小川清彦先生との出会いが私の人生の最初の大きな分かれ目でした。
大学では小川先生から大木のカケラをもらって、来る日も来る日も学校で夜遅くまで彫っていました。あれだけ無心になって、ひたすら彫刻に向かい合ったのはあの時代が一番だったかもしれません。大学では毎年夏休みに東京藝術大学の千野茂先生が集中講義として教えに来てくれていました。そのご縁で大学卒業を控えた時に、千野先生から東京藝術大学大学院彫刻科の受験を勧められ、合格することができました。私は舟越保武先生が藝大彫刻科の教職に就かれた時に入った第1期生なのですが、当時は「もの派」など、観念的な芸術が主流でしたので、具象彫刻の舟越先生にとって、アートムーブメントに傾倒していた多くの若者と異なる、私のような学生が新鮮だったのかもしれません。
Q. 色々な先生方との出会いが、安田先生を彫刻家へと導いたのですね。
安田 藝大の大学院を出た後、イタリア政府国費留学生として25歳でイタリアに渡りました。ローマ・アカデミア美術学校に3年間通いながら、イタリア現代彫刻の巨匠ペリクレ・ファッツィーニに師事しました。このローマでの生活において様々な芸術に触れる中で、私は石彫に大きく惹かれていきました。具象彫刻のファッツィーニは抽象彫刻の石彫は手掛けていませんでしたが、ある時、私が「大理石も彫ってみたい」と相談したところ、知り合いの石屋の親方を紹介してくれました。そこで少しずつ、大理石を扱う技を覚えていったのです。ところがその親方が急に亡くなられて、大理石のメッカ、北イタリアのピエトラサンタの知り合いのアトリエに移りました。1972年(昭和47年)27歳のときです。その後、ローマとピエトラサンタを行き来しながら創作活動をしていましたが、1986年(昭和61年)にピエトラサンタにアトリエを構え、今もこの街で制作をしています。
ピエトラサンタとイサム・ノグチ
Q. ピエトラサンタはどのような街でしょうか?
安田 ピエトラサンタは、世界随一の大理石採石場として有名なカッラーラから南へ20kmほど下りた麓の街です。カッラーラの大理石は紀元前1世紀半ば頃、ローマ帝国が発見したと言われています。大理石は動物や貝の死骸が海底で積み重なってできた石灰石(ライムストーン)が地中の熱と圧力により再結晶化して変質したものですが、それが地殻変動によって地上に現れたのがこの山々なのです。大昔、ローマ人がこの山の頂で真っ白な石を見つけて「ここはもしや白大理石の山なのではないか」ということで発見されたのです。それまでローマ帝国は時間とお金を掛けてギリシャから大理石を運んで使っていましたが、「最良の大理石の山がイタリアにあった!」ということで、この発見から現代に至るまで2,000年以上掘り続けられているわけです。
カッラーラの大理石は、長い年月をかけて堆積した層が斜め45度の綺麗な模様として現れているのが特徴ですが、ローマ時代から下へ下へと掘り進める中で、品質の良い大理石はだんだんと枯渇してきているのが現状です。ミケランジェロの「ダビデ像」(1504年)などにもカッラーラの大理石が使われていますが、彼の時代にはすでに良い層は取り尽くされていたとも言われています。だからピエトラサンタの石屋さんは、本当に信頼できる人にしか品質の良い貴重な石を売ってくれません。滅多に採石されない良質な大理石の大きな塊は、カッラーラの麓のピエトラサンタにいないと入手できないのです。そういう背景もあり、ピエトラサンタにはヘンリー・ムーアやイサム・ノグチなど、著名な彫刻家が世界中から集まり、彼らの創作の場になってきました。
Q. このピエトラサンタで安田先生はイサム・ノグチと出会い、その後親しく交流されたと伺っています。安田先生とイサム・ノグチの作品には、例えば建築家のデザインと共鳴して都市の中で素晴らしい空間を創造しているという部分で、何か共通する視点があるようにも感じます。
安田 そのように感じていただけるのは光栄ですが、それは意識しているわけではありません。イサム先生は先駆者ですから、色々なものと戦って世界的な評価を得られてきたわけです。
イサム先生が建築デザインとの関わりの中でつくられた作品の中で、私が素晴らしいと思っているのは、NYの「チェースマンハッタン銀行」(1961年)のサンクンガーデンです。このビルはSOM(編註:Skidmore, Owings & Merrill[略称:SOM]は、米国最大級の建築設計事務所)が設計を手掛けたもので、後に私が大変お世話になった建築家の椎名政夫さんがSOMに入社した時、最初に担当した大規模プロジェクトと聞いています。椎名さんはこのプロジェクトの模型をつくって、そのサンクンガーデンに設置するアートをアルベルト・ジャコメッティ、ヘンリー・ムーアなど、当時世界で最も著名な5人の彫刻家に案を出してもらったそうです。そして、イサム先生の案が選ばれました。
イサム先生の案は石庭のようなデザインで、地下フロアのガラス越しに見る構成になっています。SOMがつくった当初の模型には、地上からサンクンガーデンに降りる階段があったのですが、イサム先生はそれを取り払って誰も入ることができない世界をつくり上げました。このアイデアの源にはおそらく龍安寺の石庭があったのだろうと思います。NYを訪れた方は是非見て欲しいのですが、本当に素晴らしい作品です。
「触れる」という原初的感覚

Q. 安田先生のひとつひとつの作品において、それぞれのテーマや場所性があると思いますが、方向性として「柔らかな形」をした作品がいくつかあるように思います。これらの作品において共通して意識されているお考えはあるのでしょうか?
安田 難しいご質問ですね(笑)。回答になるかどうかわかりませんが、ひとつの作品についてお話させていただきます。北海道の洞爺湖畔に私の「意心帰(いしんき)」(1984年)というモニュメントがあります。これは1977年(昭和52年)に有珠山が噴火し、その翌年に発生した泥流によって犠牲となった子供のための慰霊碑なのです。泥流が起きた後、現地に伺った私は、この場所にまだ子供の遺体が埋もれたままだという話を聞いて「慰霊碑はここに設置しよう」と考えました。
慰霊碑とは、生きている人が亡くなった人の魂に想いを寄せるものです。それは「慰める」ということであったり「思い出す」ということであったりしますが、そのような時に「触れることができる」ということが、自分と自分以外のものとの対話において重要だと考えました。こういう考えで制作したのが「意心帰」です。亡くなった子供のご家族がこの作品に触れることで子供の魂と繋がりを感じる。あるいはここを訪れる多くの子供たちが楽しく遊びながらこの作品に触ったり登ったりする中で、亡くなった子供の魂も一緒に遊んでいるように感じてくれれば……と願っています。

「意心帰」(北海道、洞爺湖畔/1984年)**
安田 私の彫刻では、この「触れることができる」ということが一番重要です。人間の赤ちゃんは、お母さんのお腹の中で、脳の発達よりも先に触覚が発達するそうです。手が形づくられてお母さんの子宮の内壁に触れることが、赤ちゃんが最初に感じることだそうです。だから「触れる」という行為は人間にとって原初的なことなのです。
現代の都市は、そのほとんどが「触れてはいけないもの」で構成されています。皆が「自分のものではない、他人のものに触れてはいけません」と教えられて大人になっています。私は「都市空間におけるアートの役割」という難しいことはわかりません。ただ、「触れてはいけないもの」で満たされた都市の中で、皆さんが自然と「触れてみたい」と感じるような存在をつくりたいと考えています。

安田 有楽町の「東京国際フォーラム」にも「意心帰」(1996年)という名前の作品があります。この場所では、子供たちが彫刻を目にした瞬間、そこに向かって走り出していくような光景をよく目にします。それはなぜだろうと、私は考えるのです。それはおそらく、子供たちが自然と「触れてみたい」と感じること。そして彫刻そのものには何の意味もないことが、そうした衝動を引き起こしていると思うのです。
「特に意味をもたないが惹きつけられる」「とにかく触ってみてみたい」。そういう存在が今、世界中でどんどん無くなりつつあるように感じます。私は現代彫刻家として「触っても良い作品」をつくりましたが、そういうものをつくりたいと思った原体験のひとつをお話します。私の頭には生まれつき10円ハゲがありました。子供の頃、いつも通る田んぼ道にお地蔵さんがあったのですが、母親は私と一緒にそこを通る度にお地蔵さんの前で立ち止まって、私のハゲを優しく撫でながら「この子のハゲが治りますように」と祈っていました。当時は、私も子供心に気にしていたのでハゲを触られるのは「嫌だなあ」と思っていたのですが、母親の手から感じたその温かさは今も忘れることができません。
安田 そういう温かさを感じるものが、今世界中からどんどん消えていっているように私は感じるのです。だから形がどうとかそういうことよりも、もっと根源的な「人間はどうあるべきか」ということを、私たちはもう一度深く考えなければ、そろそろ取り返しがつかなくなってしまうように思います。
古代の遺跡から発掘される遺物に、制作者の名前は刻まれていません。しかし、はるか昔のものであってもそれが素晴らしいものであれば、人は心で感じることができます。そういう時代を超えて凄いと思えるものを私はつくりたいのです。名前が残るとか、そんなことはどうだって良いんです。
大理石の彫刻は、環境が良好なら数千年後も残ります。3,000年後か、あるいは5,000年後か。私の彫刻が時代を経て土の中に埋まり、遠い未来、地中からその一部が現れる。それを目にするある未来人は「どうせ大したものじゃないよ」と興味をもたないかもしれません(笑)。でも、本当に魂を込めてつくったものであれば、別の未来人の心を動かして発掘され、「凄いものが出てきた!」と思ってもらえるかもしれません。そういうものを私はつくりたいのです。

「意心帰」(ローマ、トラヤヌス帝の市場 インペリアル・フォーラム博物館/2007年)**
形のないものを形にする
Q. 安田先生の作品には、「天モク(※モクはさんずいに禾)」のような、門型の作品もありますね。
安田 中央の柱が地面から少しだけ離れているこの作品でやりたかったのは、まさにこの「隙間」です。天にも触れず地にも触れず、何者にも触れないからこそ、この空間に真実が宿る。天と地の狭間なので、それはとてつもなく大きな空間なのです。
若い頃、私はそういう作品をつくりたいとずっと考えていましたが、当時の私はどのように表現するのが良いのかわかりませんでした。そうした中で出会ったのが法隆寺の宮大工として著名な西岡常一さんの本でした。
そこには、法隆寺五重塔の中心に立つ心柱は「浮いている」状態であり、地震時にはこの心柱と固定されていない各層が互い違いに揺れることで建物が倒壊しないという、驚くべき内容が記されていました。この本を読んだ時、これこそ日本人の精神だと感じて、この「隙間」を表現するために、何度も石膏で模型をつくって完成させました。

「天聖、天モク(※モクはさんずいに禾/写真奥)」(長野、セゾン現代美術館/1986年)**
安田 形のないものを形にする。これが私の目指している彫刻です。冒頭に「アルテピアッツァ美唄」で取り組んでいる「こころを彫る授業」のお話をしましたが、この体験もそれが目的です。参加者は自分の心という、手に触れることができない、目に見ることができないものに向かい合う。そして邪心も含めて、自分自身の心とまっすぐに向かい合って一心に彫ることで、心が目に見え触れることのできる形として現れるのです。私は同時に「その逆」でもあることを目指しています。形というものがある。そこに作家の心や意図ではなく、見る人の心を映し出す。そういった彫刻をつくりたいと思っています。
だから「天モク」の隙間も単なる隙間ではないのです。
Q. 地についているようでついていない「隙間」。ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂に描いた『アダムの創造』のようですね。
安田 それは嬉しいご指摘です(笑)。
Q. 本日はありがとうございました。
[写真クレジット]
* 提供:アルテピアッツァ美唄
** 提供:Studio Kan

安田 侃(やすだ・かん/彫刻家)
1945年北海道美唄市生まれ。1969年東京藝術大学大学院彫刻科修了。1970年イタリア政府招聘留学生としてイタリアへ渡り、ローマ・アカデミア美術学校で学ぶ。現在、イタリア、トスカーナのピエトラサンタにアトリエを構え、彫刻の創作活動を続けている。
作品は、東京ミッドタウン、東京国際フォーラム、札幌駅、洞爺湖畔、ノーザンホースパーク、セゾン現代美術館、酒田市美術館、朱鷺メッセ、ベネッセアートサイト直島、宮崎県立美術館、トラヤヌス帝の市場(ローマ)、ボーボリ庭園(フィレンツェ)、ブリッジウォーターホール(マンチェスター)、オーロラプレイス(シドニー)、1251アメリカ街(NY)などに設置されている。また故郷の北海道美唄市に安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄がある。
2002年村野藤吾賞(アルテピアッツァ美唄)、2025年イサム・ノグチ賞を受賞。
https://www.kan-yasuda.co.jp/ja/
安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄
https://www.artepiazza.jp/
同館のイベント「こころを彫る授業」
https://www.artepiazza.jp/workshops-events/curve/